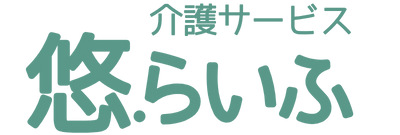認知症の方が毎日何時間も歩き続けることに悩んでいませんか?
「朝から晩まで歩き回っている」「どこかへ行こうとして止められない」「道に迷ってしまうことが増えた」――。
こうした行動は、認知症による「周辺症状(BPSD)」の一つであり、家族にとって大きな負担となることもあります。
この記事では、なぜ認知症の方は長時間歩き続けるのか? その原因と対策について詳しく解説します。
周辺症状(BPSD)とは?認知症の行動・心理症状
認知症の症状は、大きく分けて次の2種類に分類されます。
「中核症状」:記憶障害や判断力の低下など、認知症の進行とともに必ず現れる症状
「周辺症状(BPSD)」:不安・徘徊・暴言・幻覚など、環境や本人の性格によって異なる症状
「長時間歩き続ける」行動は、BPSDの一つである「徘徊(はいかい)」に該当します。
BPSD(周辺症状)にはどんなものがある?
- 徘徊(はいかい):目的なく歩き回る、外出して帰れなくなる
- 不安・抑うつ:急に泣き出す、気分が落ち込む
- 幻覚・妄想:「財布を盗まれた」「家族が自分を騙している」と訴える
- 暴言・暴力:突然怒り出す、大声を出す
- 睡眠障害:昼夜逆転してしまう
「徘徊」や「長時間の歩行」も、このBPSDの一つとして現れることがあります。
なぜ認知症の方は歩き続けるのか?その理由とは
認知症の方が長時間歩き続けるのは、単なる「運動好き」ではありません。
そこには、脳の変化や心理的要因が関係しています。
1. 記憶障害による影響
認知症では、短期記憶(最近の出来事を覚える力)が低下するため、「どこへ向かっているのか」を忘れてしまい、歩き続けることがあります。
具体的な例
「買い物に行こう」と家を出たが、途中で目的を忘れてしまい、歩き続けてしまう
「自宅に帰ろう」とするが、自分の家が分からなくなり、さまよってしまう
2. 仕事や生活習慣の影響
認知症の方は、過去の記憶が強く残るため、かつての習慣を繰り返そうとすることがあります。
具体的な例
「会社に行かないと!」 → 毎日出勤していた記憶が残っており、歩き出してしまう
「自分の家はどこ?」→ 昔住んでいた場所を探して歩き続ける
3. 不安やストレスの解消行動
認知症の方は、自分が今どこにいるのか、何をしているのか分からない状態になると、不安や焦りを感じやすくなります。
具体的な例
「何かしなくては!」という不安感から、動き続ける
家の中で落ち着かず、外に出て気分を落ち着かせようとする
昼夜逆転や睡眠障害
認知症が進行すると、体内時計が乱れ、昼と夜の区別がつかなくなることがあります。
その結果、夜中に外へ出て歩き回るケースも増えます。
具体的な例
夜中の2時に起きて「朝だから仕事に行かないと」と家を出る
家族が寝ている間に外出し、何時間も歩き続けてしまう
認知症の方の「歩き続ける行動」への対応方法
長時間歩き続けることは、健康維持には良い影響を与えますが、迷子や事故のリスクがあるため、適切な対応が必要です。
家族だけで対応しようとしない
家族だけで見守るのは、精神的・身体的な負担が大きいため、適切な介護サービスを活用することが重要です。
できる対策
散歩同行サービスを利用し、安全を確保
GPS機能付きの見守りグッズを活用(例:GPS付き靴、見守りアプリ)
本人の気持ちを尊重しながら見守る
「歩くことを止める」のではなく、安全に歩ける環境を整えることが大切です。
できる対策
安全なルートを決め、散歩を習慣化する(家族が付き添える時間を決める)
室内で歩ける環境を整える(歩行スペースを確保する)
介護サービスを活用して、負担を軽減する
家族だけで見守るのが難しい場合、専門の介護サービスを活用するのも一つの方法です。
「散歩同行サービス」を利用することで、安全に歩ける環境を確保できる
デイサービスや訪問介護を活用し、適度な運動をサポート
まとめ:認知症の方の「長時間歩き続ける行動」と上手に向き合おう
認知症の方が長時間歩き続けるのは、BPSD(周辺症状)の一つであり、不安や記憶障害が影響していることが分かります。
家族の負担を減らすためのポイント
歩きたい気持ちを尊重しながら、安全を確保する
適切な介護サービスを活用し、安心できる環境を整える
「一人で見守らなければ」と無理をせず、専門家に相談する
「認知症の方の散歩を安全にサポートしたい!」と思ったら、まずは自費介護サービスの散歩同行を検討してみませんか?
詳しくはこちら!お問い合わせ・無料相談へ